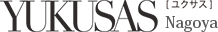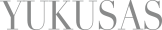老舗と気鋭店が生み出す京料理は、京文化のさらなる隆盛を支えています。京文化を担う料理人にもてなしの心と自身の物語を語っていただきました。
HAMASAKU
浜作

本物の日本料理を知るために
京都で日本料理を味わうことの大切さを解く
Q、料理をする上で大切に考えていることは。
『素材はいじりすぎない方がいい』
料理は単純なほうがいいというのが、私の一番大事にしている信条でございます。ですから、料理法に工夫を重ねると申しましても、それは下処理によって生臭みを取り、素材本来のよさを引き出すことが主眼であり、余計な飾り付けなどをせず、持ち味を生かして極力ストレートに仕上げるのが本来のお料理のあるべき姿だと思います。女性に例えるなら、素肌のお手入れも行き届いておられない方が、ファンデーションを厚く塗り、その上から、取って付けたような眉を描き、まつ毛にはマスカラを塗り重ねと、コテコテに飾り立てるようなものでございます。
大切なのは、基本的な手入れでございます。素肌美人こそがほんとうの美人なのではないでしょうか。全く和食も同じことがいえます。
素材の持つ本来の美味しさを生かすには余計なことはしない、これに尽きます。そのためには「味をつけすぎない」ことが根本的に大事になってまいります。お食事をされた後、「美味しかった」ということだけが頭に残って、お口には味がなんにも残らないほうがよろしいのです。


Q、京都料理の魅力は。
『美味しい京都料理を味わうには京都へおいでいただくこと』
昨今の安易な和食のグローバル化により、日本料理元来の良さが薄められてるように思います。
「郷に入っては郷に従え」で、海外で日本料理を作るうち、ある程度は先方の国や形式や嗜好に合わせなければなりません。また、そうしなければ先方に受け入れていただくことはできないでしょう。先方に合わせることに熱心になるあまり、往々にして「迎合」の域までいってしまいがちであります。そうなりますと本来の和食の素晴らしさが薄まり、原型をとどめないということにまでなりかねないのでございます。
日本料理の本質を変えずに根付かせることは至難の技でございます。
季節の中でも、絢爛豪華な花見の時季よりも、極彩色の中にチラホラと落葉が始まった晩秋にこそ、「もののあわれ」を感じ、哀愁を人一倍感じるのが日本人の特性であります。あえて言えば、この「たそがれ」「斜陽」「哀惜」「懐古」などなどをあらゆるところから実感できるということこそ、京都の京都たるゆえんであり、また、第一の魅力であります。
ですから本当に京都料理を味わいたい方は、食材や気候風土、設えやロケーションまで、こちらの思うように準備ができます日本へ、京都へおいでいただければと思うのでございます。
■カウンター割烹発祥の地
川端康成先生にも愛されていた「美味延年 浜作」
『「旨いもん食うなら浜作へ行け」と当時北大路魯山人のお言葉が残っているほどの腕前の料理人であった森川栄氏』
高級料理は立派なお座敷を具えた大料亭でいただくのが当たり前だった当時、極力料理そのものの鮮度や味付けに特化したこの方式は、料理業界に置ける一大革命でありました。
祖父が鮮やかな包丁さばきで、お客様の目の前で全ての料理を取り行うというカウンターオープンキッチン形式を日本で初めて行いました。
浜作は門前市を成す盛況ぶりとなり、宮様方や旧華族、財閥の長といった特権階級、いわゆるエスタブリッシュメントの方々で占められておりました。
「美味延年」とは美味しいものをいただくと長生きするという意味であり、川端康成先生にご揮毫いただいたものです。現在の浜作2階に大切に飾ってある、「古都の味 日本の味 浜作」も川端康成先生にご揮毫いただいたものです。




浜作
主人 森川 裕之(もりかわ ひろゆき) 氏
<profile>
昭和37年、京都祇園町生まれ。
日本最初の「板前割烹 浜作」の二代目森川武の長男として育つ。
青山学院卒。慶応義塾大学院中退。
平成三年、父の急逝により三代目主人となる。
今上陛下、チャールズ皇太子をはじめ数々の内外貴紳のお料理を担当する。
本店のカウンターに立ち、お客様をもてなす日々を送る。
主催する料理教室は平成29年春、通算2000回を越え今なお記録更新中。日本各地から生徒が集う。
平成25年に「和食の教科書 ぎをん献立帖」平成27年に「和食の教科書・ぎをん丼手習帖」、平成29年「京料理の品格」を上梓。
趣味は、クラシック、オペラ、歌舞伎、文楽と多岐にわたり造詣も深い。
電話 075-561-0330
店名 浜作
住所 京都市東山区祇園八坂鳥居前下ル下河原町498
URL http://kyoto-gion-hamasaku.com/
営業時間 17:00~
定休日 水・最終火曜日
KENNINJI GION MARUYAMA
建仁寺 祇園 丸山

■「思い出」とともにいただく 心を伝える京料理
「高台寺土井」さんで10年間奉公し、「菊乃井」さんで料理長を7年半、「和久傳」さんで総料理長を5年間勤めました。祇園でお店を出せたのは、自分を育ててくれた修行先のお店さんとの出会いがあったからこそだと思っています。中でも土井さんは敷地が2000坪ある料亭。政治家の方々や画家、音楽家など角界の著名な方々がいらしてたんです。その時、同じ空気を吸わせてもらったことが何よりも刺激になりましたね。
京料理は、日本人の感覚を伝承し、思い出の情景を演出するものです。例えば、夏といっても、初夏、真夏、夏の名残があります。その時期が訪れると、蛍とか夕立とか思い浮かぶように料理には、匂いや味があり、思い出の引き出しを引っ張る要素になるんです。あの時はこんなん食べた、あんなん食べたとか。そして、懐かしい郷土の料理は、美味しいとか味じゃなく、思い出なんです。運動会で食べたお母さんが作った白いおにぎり。おじいちゃんと食べたお煎餅、蛍の香り、夕立があがったときのにおい、兄弟とスイカを一緒に食べたとか。そんな夏の思い出のシーンを蘇らせて楽しんでもらえる料理を表現したいと常に考えています。
日本料理は生命が感じられる料理なんです。けん、つま、あしらいなどを用いるのもそのためです。丸山では、庭の緑、設えも考慮された光・音・リズム・香り・味、見えない5つのものを感じていただくことを大切にしています。

二階お座敷。優美で涼やかなひと時を演出してくれる。


庭の景観。細部にまで手入れが行き届いた美しい和の空間が広がる。
■こだわりの空間を飾る 掛け軸と器
時々聞かれます。なんでこんな軸かけてるのと。例えばこれは、かたつむりの掛け軸(熊谷守一(くまがいもりかつ)氏作)なんですが…これはかたつむりが通った後に、銀色の道をつくってるんです。これは、次に迷った人がぶつかったときに先人が作った道を表してるんですよ。そして、なぜかたつむりか。目が飛び出てるでしょ、未来を見ているんです。
他でいうと、川崎小虎(かわさきしょうこ)の西瓜の掛け軸の西瓜には虫がついてる。日本人の感覚で伝わるものが、ここに盛り込まれているんです。一つひとつに、生きる上での心得というかメッセージが込められてるんですよ。おかしな話だけれども、こういった感性の部分を日本の人にも分かっていってもらいたいですし。勿論、海外の人にも伝えていきたいから飾ってます。
器も同じです。魯山人の言葉ですが、同じ冷奴でもギヤマンにのってるのは美味しいと。器で美味しさは変わるんです。宇野千代さんと一緒に作った湯飲みもあります。わからなくても、何かいいなと感じられる、一流の名品がここにはあります。こういったものを少しずつためてお出ししてるんです。特に古美術が好きなお客さんに喜ばれますね。
■伝統を続けてこそ生まれる 新しい京料理
近頃のお店で出している料理は心が抜けているなと感じることがあります。日本料理の美味しさを伝えるイベントに参加し、ニューヨークにご飯を炊きに行った時の事です。当初は、すでに炊いているものを食べていただく予定だったのですが、炊きたてのご飯を味わってほしくて変更してもらったんです。するとお客さんは美味しいものを食べるために炊けるまでの30~40分間待ってくれてるんですよ。お客さんに早く料理をお出ししてあげることも勿論大事です。しかし本当に美味しいものを召し上がっていただくために、待ってもらうことも大事なことなんです。お茶事でも時間をかけてもてなします。こういう心がもっとあって欲しいと思ってしまいますね。伝統が変わらずに受け継がれてきたのは、新しいことを続けた中から生まれてくるからなんです。古いものを守るため、伝統を支えるために、新しいことをするんです。
京料理の文化も、受け継がれたものを変わらないようにずっとやり続けて、その中で時の流れ、うねりに任せて変わっていけばいいと思います。変えることを前提にする必要はないと思います。
■弟子たちへ説く心得とは
真摯な心をもつことはもちろん一番大事なのですが、結果も同じくらい大事。プロとして生きていく、ご飯を食べていくにはある程度のレベルまで、結果を残さないとならないんです。自分で考えて、取り組んで作る。そうして、自分の力で生きていけるレベルになったら、その時に初めて自分が好きなもの。個性や特性、自分の色を出していいと思います。それまでは、他への批判をしたらならないと思っています。他にも、白木、畳などの生を感じられる内装へのこだわり、一軒家であること。建物が大事なんやと伝えています。ただ、良いものをみてしまうと不幸やとも言われます(笑)。
それでもただパッとみて深く知らないまま見よう見まねでやろうとするのはあかんと思います。背景や文化を踏まえ、じっくりと成熟してほしいです。例えば井戸を掘って、京都の水をひくことなど、見えないところでもしっかりと京都の文化に根付いた考え方であってほしいですね。


紫陽花盛り
硝子 (百合根すり流し おくらとろろ トマト 寿海苔 南瓜 海藤花 ふり袖)
小芋土佐煮 唐もろこし 焼穴子
小袖寿司(小鯛 酢立挟み)江戸生姜
ふかひれ煮凍り ほじそ 生姜酢ジュレかけ
日向夏釜 (蛸柔煮 生うに 豆乳半張り)
夏の風情を表現したダイナミックな一皿。季節は六月の半ば、紫陽花の生命が力強く、そして美しい。黄色の大きな器は石井康治氏作。日向夏を絞ってもらうことによって香りを引き出す。クリスタルの硝子器の百合根すり流しは大人気。日向夏の器は柿右衛門作。ほか三田青磁など、三色カラフルは江戸切子。

暑気払い 冬瓜釜(温)
梶の葉蓋 祇園丸山
鮑柔煮 車海老
枝豆豆腐 束ね湯葉
じゅんさい 忍生姜 ふり酢立
出来立ての冬瓜釜は熱々のものを。中にはとろける青豆豆腐にと鮑が隠れている。

祇園丸山
店主 丸山 嘉桜(まるやま よしお) 氏
<profile>
1949年 家業鮮魚商の長男として京都市中京区で生まれる
1967年 裏千家名誉師範 西脇宗妁に師事『高台寺土井』で修業に入る
1976年木屋町『菊乃井』(現在露庵菊乃井)の料理長を務める
祇園は京都の中主人丸山嘉桜が祇園丸山を開店後
1983年 高台寺『和久傳』にて料理長を務める
1988年『祇園丸山』を開店する
1998年 建仁寺南側八坂通りに『建仁寺祇園丸山』を開店
2001年 祇園丸山』リニューアルオープン
2007年 アメリカNYでの日本料理アカデミーNY事業に参加
2008年 NHK近衛家特集・NHKハイビジョン特集 桂離宮にて料理を手掛ける
2009年『祇園丸山』『建仁寺祇園丸山』両店がミシュラン二ツ星を獲得
2013年 映画『利休にたずねよ』にて料理を手掛ける
2015年『あさが来た』にて料理を手掛ける
海洋深層水で作られた京番茶も監修。
【祇園心茶】舞子さんお薦め、海洋深層水で作っています。
詳しくはこちらから>>>
店名 建仁寺祇園 丸山
住所 京都府京都市東山区建仁寺南側
営業時間 昼 11:00 ~ / 夜 17:00 ~
定休日 不定休